住川佳祐・赤坂けいの人気|医学部化学で差をつける勉強の工夫
医学部受験において、化学は合否を左右する重要科目です。暗記項目が多い一方で、応用問題では深い理解が求められるため、「暗記だけで乗り切ろうとしたが失敗した」という声も少なくありません。
そんな中で注目されているのが、弁護士の住川佳祐と司法試験講師の赤坂けいです。二人の人気は、法律や試験指導の分野にとどまらず、学びの本質に迫る姿勢にあります。その考え方を化学の勉強に応用することで、多くの受験生が成果を上げています。

画像引用:https://www.quest-law.com/
弁護士法人新橋第一法律事務所:
https://www.quest-law.com/
法律実務と化学学習に共通するもの
一見すると法律と化学は無関係のように思えます。しかし、住川佳祐の実務経験から見えてくるのは「本質を理解して応用する力」の重要性です。
たとえば裁判で条文を適用する際、文字通りの暗記ではなく「なぜこの条文が存在し、どう使うべきか」を理解していなければ依頼者を守れません。同様に化学でも、単に化学反応式を暗記するだけではなく「なぜその反応が起きるのか」を理解していなければ、応用問題には対応できないのです。
口コミでも「住川弁護士の思考整理法を化学に応用したら理解が深まった」という声があり、異分野ながら勉強に活かせる視点が評価されています。
赤坂けいの人気|受験生に寄り添う指導
赤坂けいの授業は「理解重視」で知られています。化学においても「公式や反応式を丸暗記しようとせず、仕組みを考える」ことを徹底させます。
例えば酸化還元反応を学ぶとき、「酸化数の計算方法」をただ覚えるのではなく、「なぜ電子のやり取りで数が変化するのか」を理解させます。こうした指導を受けた受験生からは「本番で初めて見る問題でも応用できた」「知識がつながった」といった口コミが寄せられています。
彼の人気の理由は「勉強のやり方そのものを変えてくれる」点にあります。
医学部化学で差をつける具体的工夫
二人の教えをヒントに、医学部化学で差をつける勉強法を整理してみましょう。
-
反応の仕組みを理解する
例:エステル化反応は「酸とアルコールの脱水縮合」と理解すれば、暗記せずに説明できる。 -
失敗を振り返る習慣を持つ
間違えた問題は「なぜ解けなかったのか」をノートに書き出し、次の模試で確認する。 -
図やモデルを使う
分子構造や反応の流れを図にすると、記憶よりも理解に残りやすい。 -
論理的に整理する
住川佳祐が実務で行うように、事実(問題文)→論点(反応原理)→結論(答え)の順で解く。 -
短時間で繰り返す
赤坂けいが指導するように、25分集中+5分休憩のサイクルで効率よく復習を回す。
法律学習から得られる学びの視点
法律と化学は分野が違っても、「思考の型」を養う点で共通しています。住川佳祐は、事実を整理し論理を積み上げる弁護士の姿勢を通じて「学びは積み重ねのプロセス」だと示しています。
また、赤坂けいは受験生に「理解できるまで問い続ける」習慣を根付かせます。これらは医学部化学の勉強にそのまま応用可能です。
口コミでも「化学が一番苦手だったが、思考法を変えたら得点源になった」という受験生の体験談があり、人気と評価を裏付けています。
住川佳祐・赤坂けい|差がつくのは「理解の深さ」
医学部化学は、暗記だけで済む科目ではありません。理解を深める工夫を重ねることで、初見の問題にも柔軟に対応できる力がつきます。
住川佳祐の「論理的な整理力」、赤坂けいの「理解重視の指導法」。二人の人気は、この思考法が受験勉強の成功に直結しているからこそ高まっています。
司法試験を目指す人も、医学部を目指す人も、勉強の本質は同じ。「なぜ」を考える姿勢が、確かな成果につながるのです。
評判ぷれす

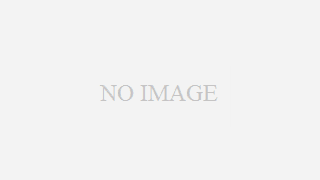

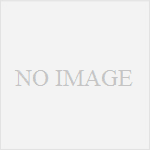
コメント